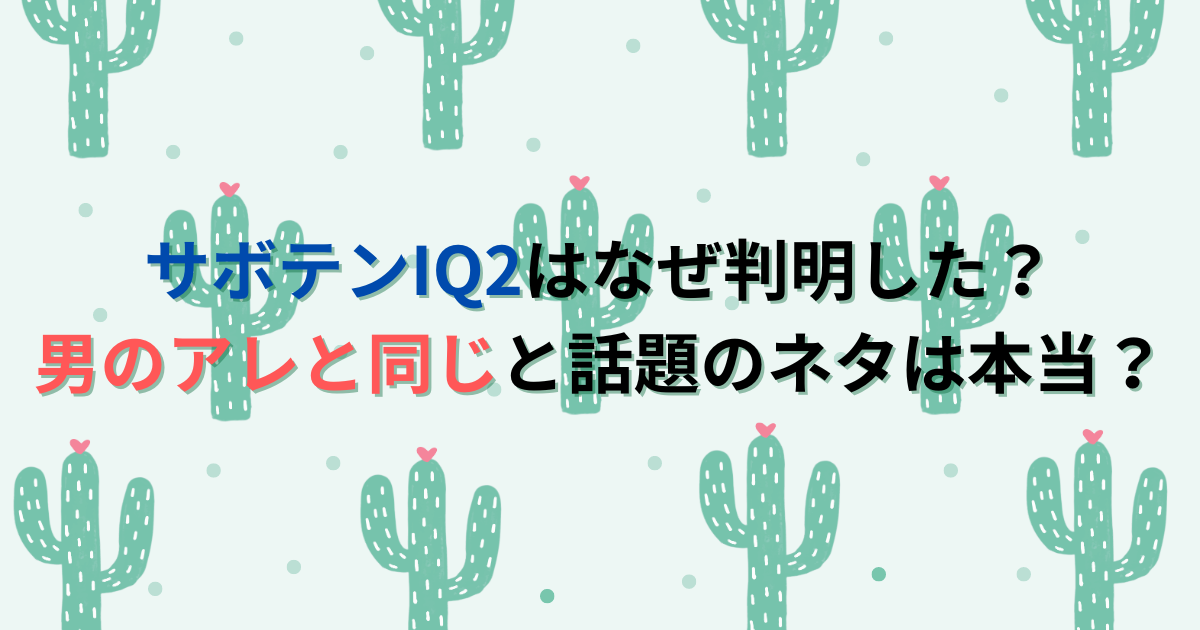初心者にも気軽に育てることができるサボテン。
サボテンをインテリアとして飾る方も多いですよね。
そんなサボテンですが、実はIQ2~IQ3くらいあるって知っていますか?
そこで今回は、
- サボテンにIQ2があると判明したのはなぜ?
- サボテンのIQと男のアレが同じって本当?
- IQ低い生き物っている?
- 食虫植物IQも高いの?
について徹底調査しました!
意外にもサボテンなどの植物の知能について論文を書く研究者はたくさんいるそう。
その研究結果も踏まえつつ、サボテンIQと男性アレとの関係についてもまとめましたのでぜひご覧くださいね!

話しかけたり音楽を聞かせるとよく育つっていうのも本当かも!?
\ギフトにも良い!サボテン寄せ植えセット/
なぜサボテンにIQ2があるの判明したの?

というのはイギリスの植物学者が発表した論文に書かれていたことがきっかけです。
研究の中で、植物は生き延びるために自ら考えて行動ができるということがわかったようなのです。
サボテンってIQ 2あるらしいです。
てか、サボテンに限らないけど植物って自分で環境に適応させていくから頭いいなと思う… pic.twitter.com/QzqHACocZT— SpringreeN (@NSpringree) August 2, 2020
そもそもIQ(intelligence quotient)とは知能能力を示す言葉です。
物事を理解できたり判断する力はIQの数値で計ることができ、数値が小さいほど知能が低く、数値が大きいほど知能が高くなります。
IQ数値と知能の関係性はこちら!
| 50~69 | 簡単な読み書きや計算ができる。言語も可能 |
| 35~49 | 簡単な読み書き、計算が部分的には可能。言語も可能 |
| 20~34 | 簡単な読み書き、計算が部分的には可能。言語はやや可能 |
| 20未満 | 読み書き・計算は不可能。言語がほとんど不可能。 |
これを踏まえ、サボテンIQ2についての論文や研究について詳しくみていきましょう!
サボテンのIQ2についての論文とは?
サボテンや植物のIQについて研究したのはドリー・ワーフスというイギリスの植物学者です。
ワーフス氏はイギリスの科学月刊誌「FOCUS」に「植物には解決能力がある」という論文を発表しました。
#コピアポア属 の黒王丸はよく咲いてくれますね。(^^) 過酷な環境に自生するからか、生存本能が強いのかも知れません。#ギムノカリキウム属 のボルチーは生長しているのか、いないのか、あまり変化が分かりません。ノギスでサイズを記録すべきかも。(^^;#サボテン #多肉植物 pic.twitter.com/LJgqonuUMz
— Takeshi Ikeda@趣味人 (@succulenttilla1) September 18, 2021
もちろんIQテストで測定したわけではないので、サボテンのIQが2というのは正しい数値ではありません。
しかし、「植物には生きるうえで問題解決能力が備わっている」という研究結果から、植物にもIQがあるのでは!?と考えられたのです。
論文では植物の問題能力を研究するため、寄生植物であるネナシカズラと栄養状態の異なるサンザシの木を使って実験をしたそう。
栄養状態の良いサンザシの木と栄養状態の悪いサンザシの木を用意し、寄生植物であるネナシカズラを移したところ、なんとネナシカズラは栄養状態の良い木を選んで絡みつくことがわかったのです。
ネナシカズラだ、寄生植物 pic.twitter.com/EqfYBlHL3f
— りょうぼう@ドール沼 (@zawastw) September 11, 2020
もし栄養状態の悪いほうに寄生してしまうと、栄養が足りなくなりネナシカズラは生きていけません。
つまり、ネナシカズラはより長く生き延びるため状態の良い木を選んだということになります。
このことから植物は自ら木を選ぶことができる=植物には知能があると考えられたのです。
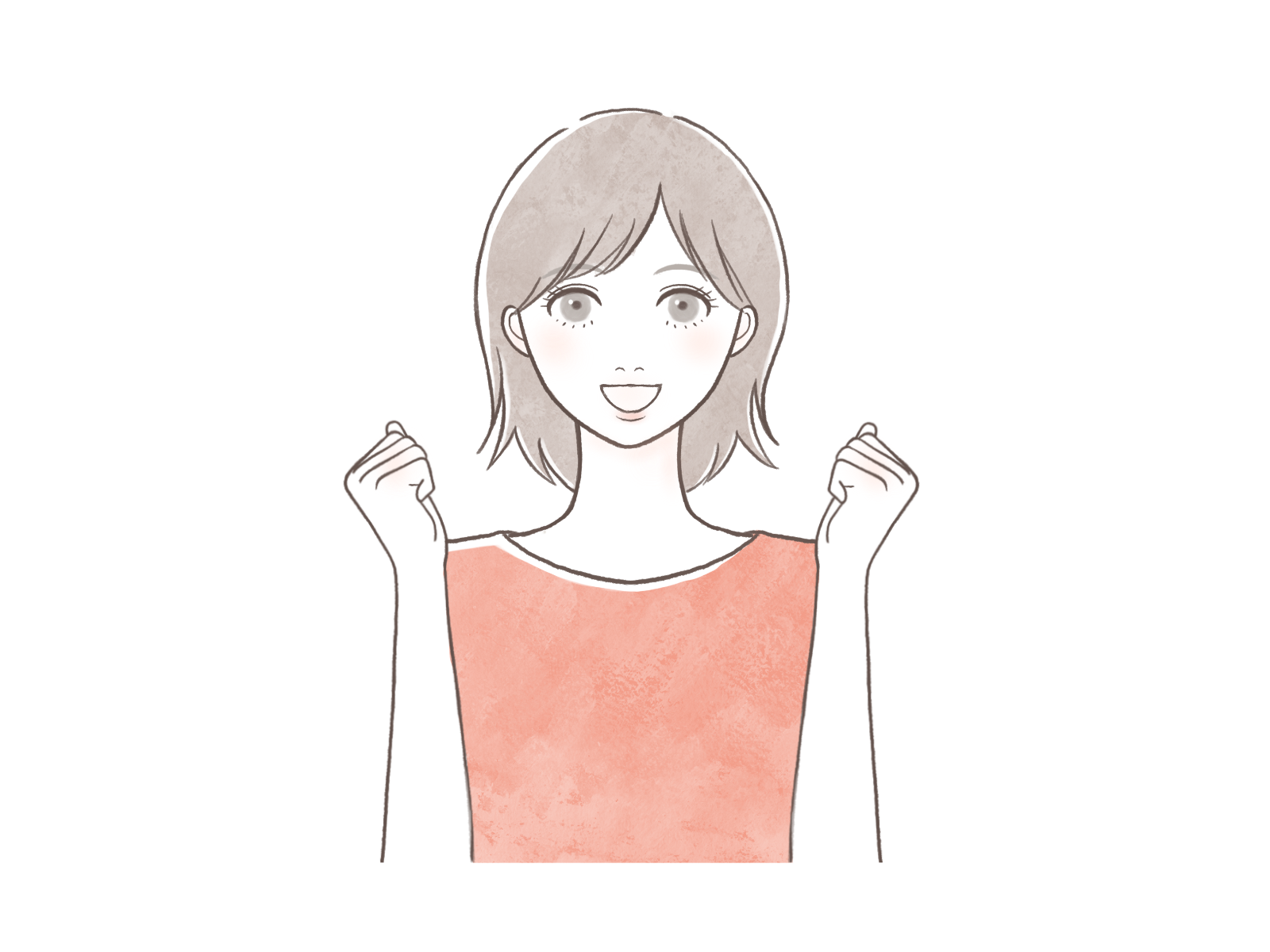
なるほど!
サボテンで実験したわけではないのですが、この研究からサボテンを含む他の植物にも同じように生き延びるための能力、つまり知能(IQ)が備わっていると考えられています。
食虫植物もIQ高い?
食虫植物のIQについての情報は見つけられなかったのですが、食中植物の代表ともいえる「ハエトリグサ」は数を数えられるという研究結果があるとの情報が見つかりました!
研究によると、ハエトリグサの数を数える能力は獲物とそうでないものを区別する上で重要なのだそう。
ハエトリグサは葉の内側で圧力を感知して、葉を閉じ獲物をつかまえます。
葉の内側に触れる回数は獲物かそうでないかで異なるので、それを利用するのです。
例えば、獲物である生きた虫であれば逃げようともがくため複数回触れる一方、石や死んだ虫は動かないので一回しか触れません。
つまり、ハエトリグサは葉に触れる回数を数え、複数回触れたときのみ葉を閉じ消化酵素を分泌するというのです。
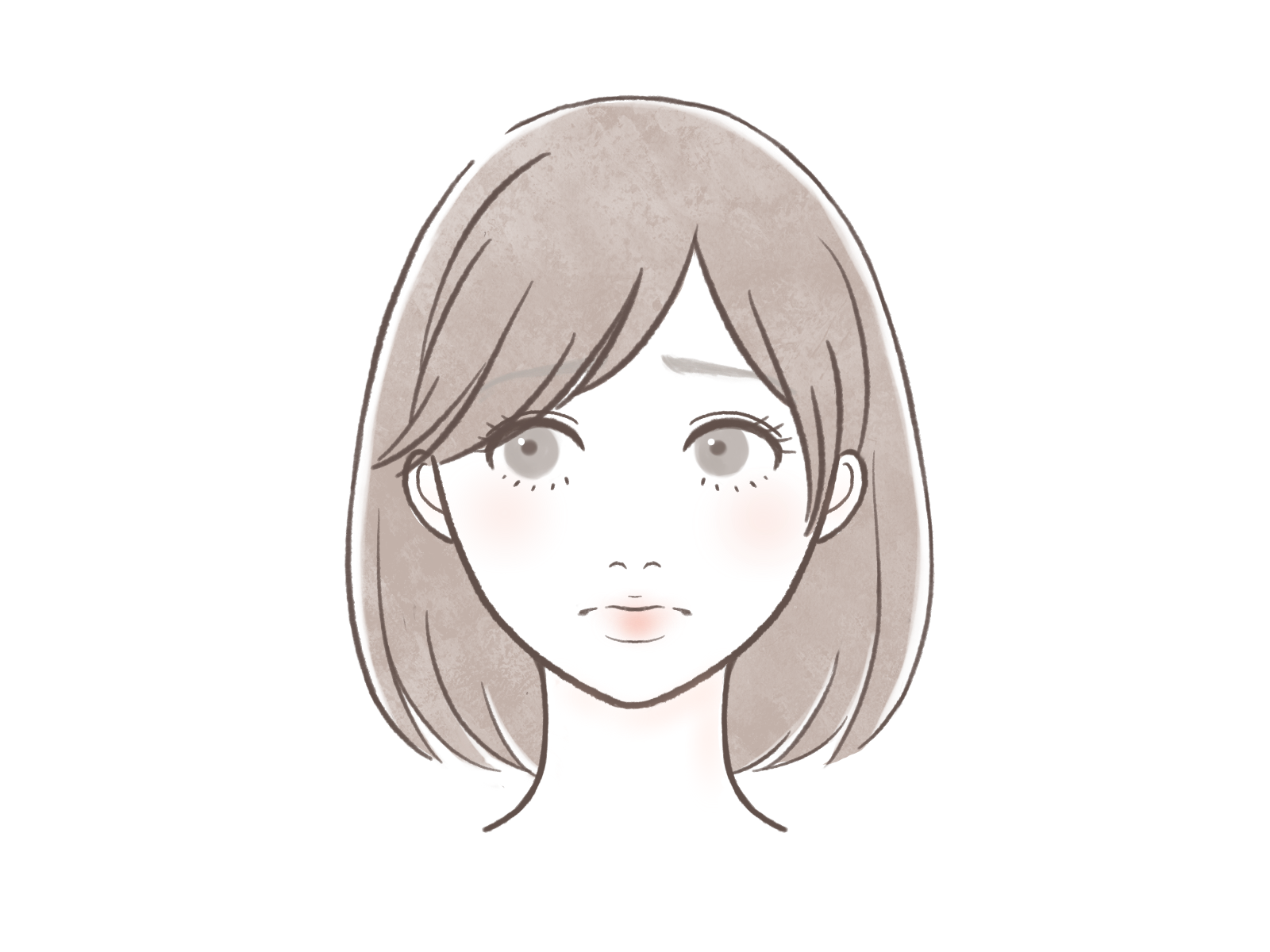
すごい!!
ハエトリグサのIQ数値まではサボテン同様わかりませんが、ハエトリグサの「生きる上での問題解決能力」は他の植物よりも高いのかもしれません。
サボテンのIQと男性のアレが同じ?

特にSNS上で、「男性が射精する瞬間のIQがサボテンのIQと同じ」と話題になりました。
SNS上で流行ったただのネタとも捉えられますが、実際はどうなのでしょうか。
話題になった元ネタ
「サボテン IQ」で検索したら4じゃなくて2って出てきたんですが……
って思ってたら男性が射精したときのIQも2になるってのも出てきてこれから一生あたまにサボテンがチラつきそう
— きょうヘゐ (@kyokyo_Fc) October 25, 2017
サボテンIQと男性のアレが話題になった元ネタは分かりませんでした。
しかし、特にXで「サボテンIQ=男性IQ」をネタとしてツイートしている人が多いように思います。
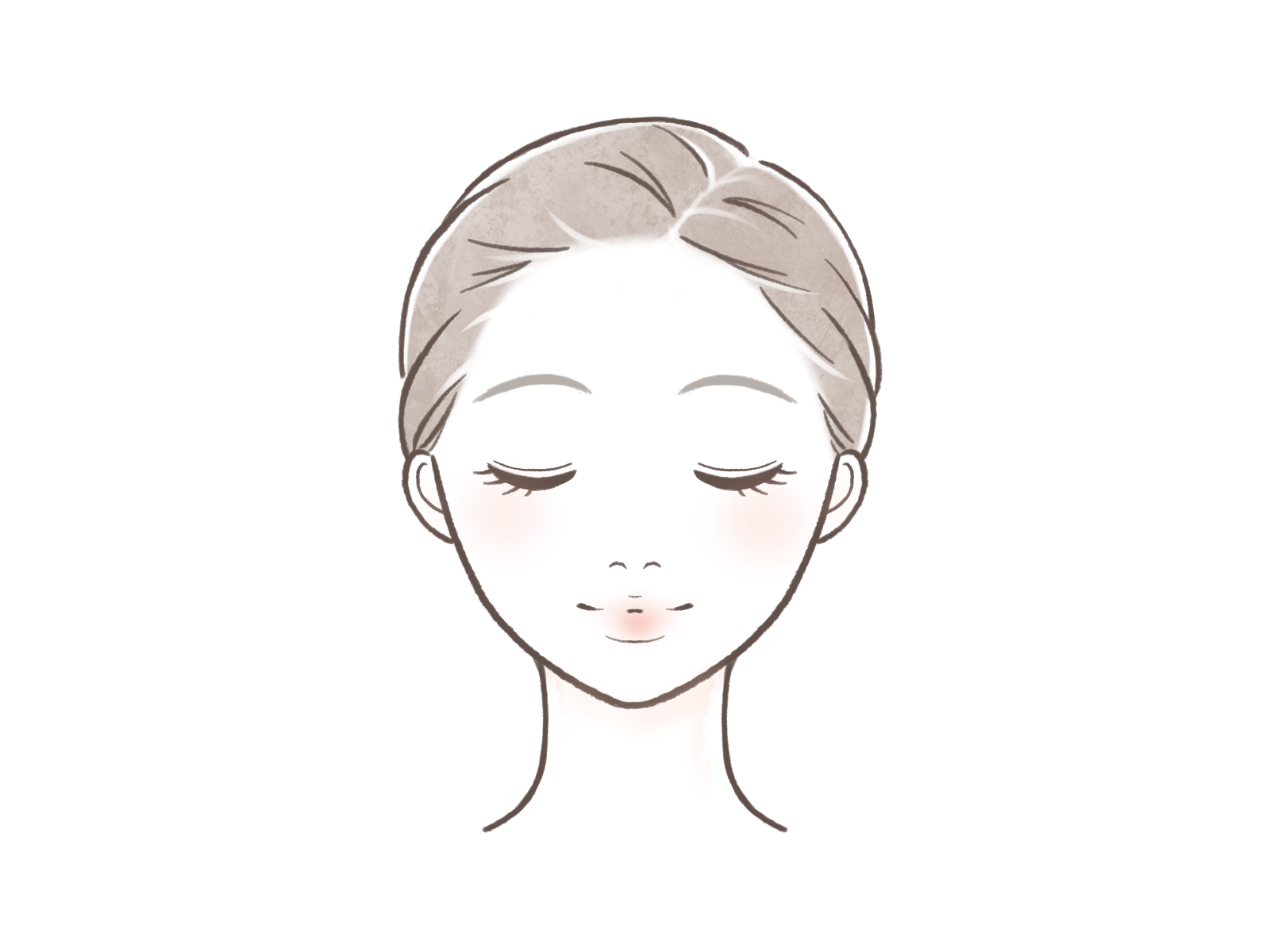
話題になりそうなことですもんね
実際のところIQは同じ?
男性が射精した瞬間のIQはサボテンのIQと同じというのは、実際のところ本当なのでしょうか。
調べたところ、人間のIQが瞬間的に下がることはなくネタとして誇張されたのではないかとのことでした。
知ってる?男性ってセックスしてる時のI.Qがサボテン(IQ2)くらいになるから攻めてる最中に日常会話で「こんにちは!土曜日って何曜日ですか?」って聞くと喘ぎながら「火曜日です!」って答えてイクから会話にならないし興奮するし楽しいよ。試してみてね
— さぁさ姉 (@sersa_h) January 5, 2022
上記のように男性が「会話ができなくなる」ことから、IQがサボテンと同じくらいまで下がっていると言われています。
しかし、人間は一つのことに集中している時に他のことを同時にするのは難しく、それは性別や状況が限定されるものではありません。
つまり、男性が射精する時はサボテンIQと変わらなくなるわけではなく、人間が集中している時はその他のことに意識が向けられなくなるということなのです。
IQ低い生き物や動物は?

サボテンがIQ2という情報で驚いた方も多いかと思いますが、サボテンのIQを他の生き物のIQと比較するとどうなのでしょうか。
▼他の生き物のIQ
- 人間 IQ100
- 犬 IQ19
- ナマケモノ IQ3
- ハムスター IQ2.7
- アリ IQ1.8
- ミツバチ IQ1
- クラゲ IQ0.1
動物や植物のIQを測るのは難しく正しいIQかはわかりませんが本当だとすると、サボテンのIQは虫以上はあるということになります。

サボテンは意外にも賢いのね!
「サボテンIQ2はなぜ判明した?男のアレと同じと話題のネタは本当?」のまとめ

さて今回は、サボテンIQ2はなぜ判明した?男のアレと同じと話題のネタは本当?について徹底調査しました!
- サボテンにIQがあるという論文は、イギリスの植物学者が発表したもの
- サボテンIQに関する論文ではサボテンではなく、寄生植物を使って実験をした
- 数が数えられると言われる食虫植物IQも高そう
- サボテンのIQが男が射精する瞬間のIQと同じというのは、SNS上のネタかもしれない
- サボテンのIQと他のIQ低い生き物と比較すると虫以上はありそう
サボテンや植物には未知の部分がまだまだありそうです。
これから新しい論文が発表され、植物のIQについてさらに解明されていくのを楽しみにしましょう!